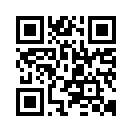2009年05月28日
2009年04月21日
2009年04月18日
スポーツから故郷を変える
2009年04月10日 (金)
NHK 視点・論点 「スポーツから故郷を変える」
法政大学教授 山本 浩
勝負をかけた試合のニュースが、画面を賑わしています。一方で、新たな学年に進んだ子ども達のボールを追いかける元気な声も響いているはずです。どこもかしこもスポーツ一色のように見えますが、その恩恵から遠く離れている人も少なくありません。遊ぶ場所も時間も仲間も見つけにくく、身体を動かす機会が減った。お腹の周りが気になり始め、ちょっと歩くだけでも動悸がするようになった。年とともに、立ち上がるのがおっくうになった。様々な世代で悩んでいる人がいるはずです。
そんな社会にスポーツが果たす役割は少なくない。それが、スポーツを楽しみ、スポーツを教え、スポーツを支える人達の思いではないでしょうか。とりわけこうした悩みに対応できる試みとしていま全国に展開されているのが、総合型地域スポーツクラブです。この総合型地域スポーツクラブは、名前を覚えにくいのが難点ですが「地域住民が主体的に運営するスポーツクラブの形態」として、「中学校区程度」の地域で、地域住民の誰もが参加できるスポーツクラブのことを指しています。特徴は多種目、つまり1つの競技だけをするのではなく、複数の種目あるいは文化活動をすることをうたい、多世代、つまりある年代のグループに偏ることなく子どもからお年寄りまでをターゲットにしたものなのです。
地域にスポーツクラブをという声が上がったのは、最近のことではありません。昭和52年、海部元文部大臣が「地域住民が参加するスポーツクラブの活動促進のための助成措置」に言及していますが、実際に動き始めたのが平成7年の事です。国のモデル事業としてのスポーツクラブ育成の施策でした。この当時は、文部省が市町村に対して補助事業をしていました。
本格的な事業への切り替え宣言とも言えるのが、2000年に当時の文部省が定めた「スポーツ振興基本計画」です。この計画には、そもそも3本の柱が立っていました。
1番目は、生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実です。思い描いていたのは、総合型地域スポーツクラブです。このとき、10年をかけて全国の自治体、市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを作る事が目標でした。
2番目は、国際競技力の総合的な向上方策。いわば、メダルが沢山取れるように力を入れようという方針です。
そして3番目が、そうしたスポーツを学校体育や学校スポーツと結びつけていこうというものでした。
今年はスポーツ振興基本計画が示した目標設定から9年目です。全国の市町村に少なくとも1つ総合型のスポーツクラブが設置出来たのは、58%とされています。多世代、多種目のクラブ活動を進めようと始めた運動は県によっては富山県や兵庫県のように早々と100%の市町村に総合型スポーツクラブがうまれた所もあります。クラブの数は去年の7月の段階で2、768になりましたがそれでも、まだ4割の自治体にはスポーツクラブがないのが現実です。あと1年半で目標を達成できるのか。現状ではやや難しいようにも思います。
クラブでやれそうなことはいくつもあります。
一つは高齢化社会に対応した老化防止の役割、さらに中年以降の生活習慣病の予防効果です。自分の身体を動かして、エネルギー消費をする傾向が薄まる時代に、大きな力になってくれるのではないかと期待がかかります。
二つ目は、子どもの体力向上です。文部科学省が毎年行っている子どもの体力・運動能力調査によれば、2007年度の小学生を、子ども達の親の世代に相当する1985年度と比較した場合、体格では向上しているが、体力・運動能力では男女ともに全ての項目で低下が見られるとしています。しかもスポーツの実施頻度で、週3日以上を条件とした「毎日やっている」子どもの割合が減っていると指摘しています。
子どもの体力・運動能力の低下傾向は、今に始まったことではありません。1985年頃にはこうした傾向が出始め、状況を深刻に受け止めた文部科学省がスポーツ振興基本計画の見直しの時期に当たった2006年に重点項目の順番を並べ替えて、3番目に考えられていた子どもの体力向上を最重点項目に上げる方針を示したほどでした。
確かに健康維持に貢献するスポーツの効用は、いまでは誰もが認識している所ですし、老化の防止や生活習慣病の予防を考える人達の参加を促してくれる力になるはずです。
元来スポーツは、様々な力を持っています。競技スポーツは、する人達には達成感、勿論落胆もたまにはありますが。見る人にも爽快感や感情の起伏をもたらします。一方で、クラブに代表される楽しむスポーツは、健康維持に代表されがちですが、どちらももっと違った側面を持っています。それが、社会を作る力です。厳しい練習をこなし、統一のとれた動きで勝利を目指す競技スポーツ。楽しさを第一に考えて、和気藹々と身体を動かすクラブのスポーツ。ともに、仲間があり、競い合うライバルがあり、そこにコミュニケーションが生まれ、やがて社会が作られていくのです。
わたしたちの身の回りから失われたのは、ストリートサッカーをする道ばたや、三角ベースをする広場だけではありません。仕事や勉強に追いまくられて、遊ぶゆとりも失いました。時間と空間を同時並行で失い、なお同じように大切なものも失いかけています。それが、身近だった人と人との距離、人間関係なのです。市場原理の中、競争社会にいるという現実が、四六時中自分を磨き、相手を凌駕することを究極の目標であるかのように錯覚させ、気が付いてみれば、自分と隣の人とは常に競い合い、優劣を争う関係なのだと信じ切っていたのではなかったでしょうか。
スポーツが装いを変えたのが、数字という衣装をまとうようになってからです。思えば、わたしたちは、スポーツに数字を求める傾向をずっと強めてきました。新記録の樹立、メダルの数、連覇の長さ、勝ち点の大小。どんなに時間をかけたものでも、どれほどの努力を積み重ねたものでも、1つの数字に代表されてしまうことがある。スポーツを翻訳する力を持った数字ですが、わたしたちが話題にしてきた数字は、あくまでもスポーツの一面でしかないのです。
その観点から見れば、クラブがもたらしてくれるのは、数字とはかけ離れたものです。血圧の測定や血液検査で知ることの出来る数字とはまったく別の、何か具体的な数値で評価できない「関係」というものではないでしょうか。この「関係」、つまりそれは「社会」を構成する要件なのですが、「関係」を築くチャンスを与えてくれることでもあるのです。数字のように瞬時に理解し、すぐに伝えられる記号ではありませんが、じっくりたまり、じわじわ感じ、時間がたっても風化しないもの、それこそがスポーツによって生み出される「関係」、「社会」が必要とする構成要素ではないでしょうか。
総合型地域スポーツクラブは、分かりやすい「健康」との関わりを前面に打ち出すスタイルでこれからも全国の自治体に増えていくのでしょうが、それを支えるのは、体力が維持できればそれでよしという一面的なものではないのです。極論すれば、1人ででもしっかり運動すれば健康維持は可能です。
しかし、「関係」を作り育てることは1人では出来ません。話しをし、会話を交わし、時には議論を延々続けるような仲間がいなければ成立し得ないのです。
総合型地域スポーツクラブが、多くの人達に参加を呼びかけるのは、クラブの運営にそれなりの経費がかかる、それを負担する人を一人でも増やしたいというのも事実です。しかし、それだけではありません。「関係」を様々な距離で色々な人との間に生む機会を増やす。1本の交流のラインだけでなく縦にも横にも斜めにも話が出来る仲間がいる集まりにする。そうした多様な可能性を持つ社会を構成するためには、それなりの人の参加が必要だからです。そこから生まれるのは、1人の身体の健康だけではなく、地域の健康、社会の健康であることを忘れないでおきたいと思います。
NHK 視点・論点 「スポーツから故郷を変える」
法政大学教授 山本 浩
勝負をかけた試合のニュースが、画面を賑わしています。一方で、新たな学年に進んだ子ども達のボールを追いかける元気な声も響いているはずです。どこもかしこもスポーツ一色のように見えますが、その恩恵から遠く離れている人も少なくありません。遊ぶ場所も時間も仲間も見つけにくく、身体を動かす機会が減った。お腹の周りが気になり始め、ちょっと歩くだけでも動悸がするようになった。年とともに、立ち上がるのがおっくうになった。様々な世代で悩んでいる人がいるはずです。
そんな社会にスポーツが果たす役割は少なくない。それが、スポーツを楽しみ、スポーツを教え、スポーツを支える人達の思いではないでしょうか。とりわけこうした悩みに対応できる試みとしていま全国に展開されているのが、総合型地域スポーツクラブです。この総合型地域スポーツクラブは、名前を覚えにくいのが難点ですが「地域住民が主体的に運営するスポーツクラブの形態」として、「中学校区程度」の地域で、地域住民の誰もが参加できるスポーツクラブのことを指しています。特徴は多種目、つまり1つの競技だけをするのではなく、複数の種目あるいは文化活動をすることをうたい、多世代、つまりある年代のグループに偏ることなく子どもからお年寄りまでをターゲットにしたものなのです。
地域にスポーツクラブをという声が上がったのは、最近のことではありません。昭和52年、海部元文部大臣が「地域住民が参加するスポーツクラブの活動促進のための助成措置」に言及していますが、実際に動き始めたのが平成7年の事です。国のモデル事業としてのスポーツクラブ育成の施策でした。この当時は、文部省が市町村に対して補助事業をしていました。
本格的な事業への切り替え宣言とも言えるのが、2000年に当時の文部省が定めた「スポーツ振興基本計画」です。この計画には、そもそも3本の柱が立っていました。
1番目は、生涯スポーツ社会の実現に向けた、地域におけるスポーツ環境の整備充実です。思い描いていたのは、総合型地域スポーツクラブです。このとき、10年をかけて全国の自治体、市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブを作る事が目標でした。
2番目は、国際競技力の総合的な向上方策。いわば、メダルが沢山取れるように力を入れようという方針です。
そして3番目が、そうしたスポーツを学校体育や学校スポーツと結びつけていこうというものでした。
今年はスポーツ振興基本計画が示した目標設定から9年目です。全国の市町村に少なくとも1つ総合型のスポーツクラブが設置出来たのは、58%とされています。多世代、多種目のクラブ活動を進めようと始めた運動は県によっては富山県や兵庫県のように早々と100%の市町村に総合型スポーツクラブがうまれた所もあります。クラブの数は去年の7月の段階で2、768になりましたがそれでも、まだ4割の自治体にはスポーツクラブがないのが現実です。あと1年半で目標を達成できるのか。現状ではやや難しいようにも思います。
クラブでやれそうなことはいくつもあります。
一つは高齢化社会に対応した老化防止の役割、さらに中年以降の生活習慣病の予防効果です。自分の身体を動かして、エネルギー消費をする傾向が薄まる時代に、大きな力になってくれるのではないかと期待がかかります。
二つ目は、子どもの体力向上です。文部科学省が毎年行っている子どもの体力・運動能力調査によれば、2007年度の小学生を、子ども達の親の世代に相当する1985年度と比較した場合、体格では向上しているが、体力・運動能力では男女ともに全ての項目で低下が見られるとしています。しかもスポーツの実施頻度で、週3日以上を条件とした「毎日やっている」子どもの割合が減っていると指摘しています。
子どもの体力・運動能力の低下傾向は、今に始まったことではありません。1985年頃にはこうした傾向が出始め、状況を深刻に受け止めた文部科学省がスポーツ振興基本計画の見直しの時期に当たった2006年に重点項目の順番を並べ替えて、3番目に考えられていた子どもの体力向上を最重点項目に上げる方針を示したほどでした。
確かに健康維持に貢献するスポーツの効用は、いまでは誰もが認識している所ですし、老化の防止や生活習慣病の予防を考える人達の参加を促してくれる力になるはずです。
元来スポーツは、様々な力を持っています。競技スポーツは、する人達には達成感、勿論落胆もたまにはありますが。見る人にも爽快感や感情の起伏をもたらします。一方で、クラブに代表される楽しむスポーツは、健康維持に代表されがちですが、どちらももっと違った側面を持っています。それが、社会を作る力です。厳しい練習をこなし、統一のとれた動きで勝利を目指す競技スポーツ。楽しさを第一に考えて、和気藹々と身体を動かすクラブのスポーツ。ともに、仲間があり、競い合うライバルがあり、そこにコミュニケーションが生まれ、やがて社会が作られていくのです。
わたしたちの身の回りから失われたのは、ストリートサッカーをする道ばたや、三角ベースをする広場だけではありません。仕事や勉強に追いまくられて、遊ぶゆとりも失いました。時間と空間を同時並行で失い、なお同じように大切なものも失いかけています。それが、身近だった人と人との距離、人間関係なのです。市場原理の中、競争社会にいるという現実が、四六時中自分を磨き、相手を凌駕することを究極の目標であるかのように錯覚させ、気が付いてみれば、自分と隣の人とは常に競い合い、優劣を争う関係なのだと信じ切っていたのではなかったでしょうか。
スポーツが装いを変えたのが、数字という衣装をまとうようになってからです。思えば、わたしたちは、スポーツに数字を求める傾向をずっと強めてきました。新記録の樹立、メダルの数、連覇の長さ、勝ち点の大小。どんなに時間をかけたものでも、どれほどの努力を積み重ねたものでも、1つの数字に代表されてしまうことがある。スポーツを翻訳する力を持った数字ですが、わたしたちが話題にしてきた数字は、あくまでもスポーツの一面でしかないのです。
その観点から見れば、クラブがもたらしてくれるのは、数字とはかけ離れたものです。血圧の測定や血液検査で知ることの出来る数字とはまったく別の、何か具体的な数値で評価できない「関係」というものではないでしょうか。この「関係」、つまりそれは「社会」を構成する要件なのですが、「関係」を築くチャンスを与えてくれることでもあるのです。数字のように瞬時に理解し、すぐに伝えられる記号ではありませんが、じっくりたまり、じわじわ感じ、時間がたっても風化しないもの、それこそがスポーツによって生み出される「関係」、「社会」が必要とする構成要素ではないでしょうか。
総合型地域スポーツクラブは、分かりやすい「健康」との関わりを前面に打ち出すスタイルでこれからも全国の自治体に増えていくのでしょうが、それを支えるのは、体力が維持できればそれでよしという一面的なものではないのです。極論すれば、1人ででもしっかり運動すれば健康維持は可能です。
しかし、「関係」を作り育てることは1人では出来ません。話しをし、会話を交わし、時には議論を延々続けるような仲間がいなければ成立し得ないのです。
総合型地域スポーツクラブが、多くの人達に参加を呼びかけるのは、クラブの運営にそれなりの経費がかかる、それを負担する人を一人でも増やしたいというのも事実です。しかし、それだけではありません。「関係」を様々な距離で色々な人との間に生む機会を増やす。1本の交流のラインだけでなく縦にも横にも斜めにも話が出来る仲間がいる集まりにする。そうした多様な可能性を持つ社会を構成するためには、それなりの人の参加が必要だからです。そこから生まれるのは、1人の身体の健康だけではなく、地域の健康、社会の健康であることを忘れないでおきたいと思います。
2009年03月28日
2009年03月28日
第4回委員会
期日:平成21年3月10日(火) 19時30分~21時
場所:ラポート会議室
議事:
①前回の確認
アンケートについて
イベントについて
②諸項目の検討
③今後の計画
実施できる種目について
④その他
場所:ラポート会議室
議事:
①前回の確認
アンケートについて
イベントについて
②諸項目の検討
③今後の計画
実施できる種目について
④その他
2009年03月28日
第3回委員会
期日:2月3日(月) 19時30分~21時
場所:ラポート会議室
議事:
①総合型スポーツクラブ創設支援事業について
②事業計画について
③アンケートについて
④今後の計画について
6月7日(日) 第1回ウォークラリーとニュースポーツ
場所:小野部田小学校とその周辺
⑤その他
場所:ラポート会議室
議事:
①総合型スポーツクラブ創設支援事業について
②事業計画について
③アンケートについて
④今後の計画について
6月7日(日) 第1回ウォークラリーとニュースポーツ
場所:小野部田小学校とその周辺
⑤その他
2009年03月28日
第2回委員会
期日:平成20年12月1日(月)
場所:サンリバー
議事:
①経過報告
5月30日の体協総会でスポーツクラブ設立を決定。
8月5日 体協小川支部役員及び体育指導委員会議において
スポーツクラブ設立に向けての話し合い
11月10日に総合型地域スポーツクラブ説明会の実施
40名の参加があった。
②今後の計画
指導者の確保について
体育施設の把握と使用状況
アンケートの実施・スポーツ教室開催・先進地視察の実施
資金について
場所:サンリバー
議事:
①経過報告
5月30日の体協総会でスポーツクラブ設立を決定。
8月5日 体協小川支部役員及び体育指導委員会議において
スポーツクラブ設立に向けての話し合い
11月10日に総合型地域スポーツクラブ説明会の実施
40名の参加があった。
②今後の計画
指導者の確保について
体育施設の把握と使用状況
アンケートの実施・スポーツ教室開催・先進地視察の実施
資金について
2009年03月28日
平成20年度第1回総合型地域スポーツクラブ説明会
日時:平成20年11月10日(月) 午後7時30分
場所:総合文化センター(ラポート) 2F研修室
内容:総合型地域スポーツクラブの意義と
設立準備・運営について
火の国広域スポーツセンター主任専門委員
中村 裕一 氏
体育協会クラブ育成アドバイザー
矢田 智美 氏
参加者:40名

場所:総合文化センター(ラポート) 2F研修室
内容:総合型地域スポーツクラブの意義と
設立準備・運営について
火の国広域スポーツセンター主任専門委員
中村 裕一 氏
体育協会クラブ育成アドバイザー
矢田 智美 氏
参加者:40名

2009年03月28日
総合型地域スポーツクラブ設立準備委員名簿
会長 宮崎 雄二
副会長 高木 弘之
副会長・会 計 那須 洋一
監 事 緒方 信俊
〃 山口 義則
委 員 福田 俊男
〃 福永 健司
〃 新開 和也
〃 岡本 泰章
〃 吉川 憲行
〃 寺本 広則
〃 豊岡 ユミ
〃 宮本 晴隆
副会長 高木 弘之
副会長・会 計 那須 洋一
監 事 緒方 信俊
〃 山口 義則
委 員 福田 俊男
〃 福永 健司
〃 新開 和也
〃 岡本 泰章
〃 吉川 憲行
〃 寺本 広則
〃 豊岡 ユミ
〃 宮本 晴隆